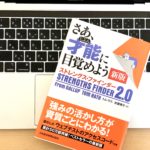ストレングスファインダーで仕事を決めてはいけない。正しい使い方を教えます
- 2020.05.02
- ストレングスファインダー

こんにちは。坂口友亮です。
今回のテーマは「ストレングスファインダーの正しい使い方」です。
ストレングスファインダーとは、「人間の強み」を研究するアメリカのGallup(ギャラップ)社が開発した「社会的に成功するための強み(ストレングス)」を発見するための診断ツールです。
Gallup社は、世界中の様々な業種の成功者200万人にインタビューを行い、成功者がそなえている34の資質を発見しました。
177問の質問に答えることで、自分を特徴づける資質のランキングを知ることが出来ます。
2020年4月現在、全世界で2300万人以上がストレングスファインダーを活用した診断を受けていて、これらのデータはGallup社の公式サイトにアクセスすると読むことができます。
…
これだけ見ると「ストレングスファインダーを受ければ、自分の強みを活かした仕事が見つかるのでは」と思うかもしれません。
しかし、この考え方には疑問符がついています。
ポジティブ心理学の生みの親、マーチン・セリグマンは次のように述べています。
- 「強み」と仕事の満足度には有意な関係があるものの、その相関はとても小さい
- その組織のなかに自分と同じ「強み」を持った同僚が少ない場合には、仕事の満足度が上がる
つまり、
- 強みを活かせば仕事の満足度が上がる、とは言い切れない
- 「その職場でレア人材である」ことが強みを活かす条件
ということです。
「科学的な適職」の鈴木祐さんも、
これらの実験はすべてGallup社が独自に行ったもので、正式な査読(専門家による内容の評価や検証)の手続きを経ていない
とした上で、
「強み」だけを頼りとして適職を探すのは得策ではない
と言っています。
この意見には賛成です。
そもそも、1つの基準だけで仕事を選ぶことは、視野を狭めるリスキーな行為だからです。
では、ストレングスファインダーを受けても意味がないのか?
僕はストレングスファインダーを正しく理解すれば、受ける意味はあると考えています。
資質はあくまで「強みの元」でしかない
ストレングスファインダーを受けると、あたかも自分に「強み」があるような気がしてきます。
しかし、診断でわかるのは、あくまで「強みの元=資質」です。
Gallup社の公式サイトでも、次のように説明されています。
才能×投資=強み
Gallup®︎
才能を強みとするには、才能への投資、才能に基づく訓練、才能への知識とスキルの付加が必要となります。
「ストレングスファインダーで資質のランキングがわかった」というのは、漫画「HUNTER×HUNTER」で言うと、
水見式を行って、自分の念能力は強化系、変化系…など6系統のうち何系なのか?がわかった段階
なのです。
強くなるには、訓練と知識が必要です。
本当に得意なことはスキルではなく「自然にできること」にある
「得意なこと」と聞くと、多くの人が
- サッカー
- 料理
- プログラミング
などの分野や、具体的なスキルを上げます。
しかし、変化の速い現代において、スキルの “賞味期限” は早くなっています。
一生かけて一つの分野を極める…という生き方も美しいのですが、環境の変化に取り残されてしまう危険性があります。
あなたの本当に得意なことは「分野」や「スキル」ではなく「自然とできる行動や思考」にこそあります。

例えば、サッカーが得意な場合でも、
- 指示を出すのが得意
- 周りの選手のモチベーションを高めるのが上手い
- 深く考えてプレーできる
- 直感で動ける
など、自然にできる思考や行動は一人一人違います。
そして、表面的なスキルや知識と違い「自然とできる行動や思考」は分野が変わっても応用することができます。
とは言うものの、普段から自然とやっていることに自分で気づくことは中々できません。
自分では気づくことの出来ない無意識の領域を明らかしてくれる点に、ストレングスファインダーの価値があります。
しかし、ストレングスファインダーはGallup社独自の調査であるため、エビデンスが十分あるとは言い切れません。
その点についてはどう考えればいいでしょうか?
相対的に考えると、アイデアがわいてくる
今後、ストレングスファインダーの第三者による研究が進んで「科学的な根拠がある」とか「ない」とか言われるようになるかもしれません。
仮に「仕事の満足度と関連が低い」という結果が出たとしても「相対的」に考えることに意味があります。
例えば、こんな話があります。
突っ込みから始まる議論、相対評価から始まる思考って、やっぱり物凄く分かりやすいんですね。
強さ議論って盛り上がるじゃないですか、ああいうの。
「いやそれは違うよ」っていうところから誰かがしゃべり出す。
すると更にそれについて複数のレスポンスがつく。
そこから話が広がっていったり、深まっていったりする。
やっぱ絶対評価って難しいんですけど、相対評価ってわかりやすいんですよ。
対立軸が発生すると面白いし、理解もしやすい、参加もしやすい。
「会議でトンチンカンな発言をするベテランエンジニア」の、深い洞察。|Books&Apps
「なぜアイデアが出ないのか?」と考えた吉田氏が打った手は、なんと、「わざとめちゃくちゃ安くてガタガタの車をつくる」という驚きの方法でした。
それはカローラと比べてどうというレベルではなく、みんなが「これはないよな」というレベルの車でした。
すると、その車を見た開発メンバーから次々と意見やアイデアが出てきたのです。
「いくら安くつくるためとはいえ、せめてここはこうしてほしい」
「さすがにボディーはなんとかしないと」
「サスペンションの品質はもう少し上げたいところ」
こうした批判を経て、次に出てきたのは、
「ここをこうすれば安くてもいいものができるのでは?」
「こうすれば買った人が誇りを持てる車になるんじゃないか」
という建設的なアイデアでした。
結果、吉田氏の狙いはずばり当たり、ソルーナの開発はここから軌道に乗ることになりました。
トヨタがわざとガタガタの車を作った理由|PRESIDENT Online
例えば「あなたの強みは?」と突然聞かれても、答えるのは難しい。
しかし、ストレングスファインダーで自分の資質を理解して
「このポイントは使えそう」
とか
「よく考えれば自分にはこんな一面もあるな」
と相対的に考えていけば、自分の強みについて理解が深まります。
強みを活かして、少しずつ人生を良くしていく
まとめると、ストレングスファインダーを活用するためのポイントは3つあります。
1. 「資質」について正しく理解する
資質はあくまで「強みの元」であり、そこに訓練や知識などを投資することで「強み」になる。
2. 表面的なスキルではなく、自分が「自然とできる行動・思考」を理解する
時代が変わっても、業界が変わっても使える「あなたの強み」になる。
3. ストレングスファインダーを盲信するのではなく「思考のきっかけ」にする
漠然と「自分の強みは?」と聞かれても答えられないが、診断結果をフックにして思考を進めることに意味がある。
ポジティブ心理学でも、自分の強みを生かすように意識しながら毎日を送れば、日常の幸福感が少しずつ高まっていくことが、くり返し報告されています。
ストレングスファインダーの結果を正しく活用するために、ぜひ参考にしてみてください。
-
前の記事

「アスリート セカンドキャリア 成功」で検索するのをやめた方がいい3つの理由 2020.05.01
-
次の記事

「今の自分にできること」でセカンドキャリアを選んではいけない 2020.05.06